営業8年目。これまでいくつかの商材で、いわゆる「自アポ自営」つまり、自分でテレアポしてアポを獲得して、自分で営業に行くスタイルを経験してきました。
過去、ブログの方でもテレアポのリスト戦略について書いたのですが、データを見ると「電話営業 つらい」「テレアポ 嫌」というワードで検索されているようです。

私はMBTIもI(内向的)のタイプで、プライベートでも電話が好きではない方です。メッセージ派で、話すのも得意ではない。
なので、今まで何度も「電話したくない」「電話することが怖い」「仕事を辞めたい」と思ってきました。
それでも試行錯誤を繰り返し、工夫を重ねてきた結果、いつの間にか「アポの神様」と呼ばれるようになっていたのです。
営業成績も2年目で全国トップになり、社長賞をいただきました。
私がどんな風に電話でアポを取れるようになっていったのか、その過程を赤裸々に書いていきます。
営業に悩んでいる方、これから営業を始める方の参考になれば嬉しいです。
できるだけ感情を入れない
「今日電話したくないな」「やりたくないな」と思って電話していると本当にアポは取れません・・。
先日noteで公開した「バンドゥーラ心理学の自己効力感(自信)」を基に、自己効力感によって営業成績も変化してくるというアメリカのデータを紹介しました。
私の経験上、私自身だけではなく、新卒・既卒の若手社員たちを見てきて、テレアポでアポが取れるかどうかは、能力ではなく、考え方・メンタルの影響が大きいと考えています。
イヤイヤで電話していると、気持ちが相手にも伝わります。
皆さんも、買い物に行って接客を受けている時「この店員さん、仕事やる気なさそうだな」「顔が死んでいるな」とか思ったことありませんか?
私はそういう店員さんからものを買いたいとは思いません。
できるだけ自分の感情は入れずに、負の感情はゼロにして「無」になって集中してコールを回すことが意外と大切で、アポを取るコツでもあります。
テレアポの目的を認識する
テレアポは、「契約を取らなければいけない」わけではないのです。
まずアポ獲得が目的です。
アポ無しに契約はありません。
アポが取れるようになるまでは、興味を持ってくれたらすぐ「時間設定」の話をして、アポを取る感覚を覚えましょう。
アポが取れたら「自分が取ったアポイントが営業でどういう結果になったのか」が気になり、その結果を見て少しずつ「契約に繋がるアポイントを取りたい」という意識になると思います。
しかし、「まだアポを取る感覚がつかなめない」「アポが取れていたのになぜか最近アポイントが取れない」という方は一旦、「時間設定」をすればいい、と気軽に考えて電話していきましょう。
トークスプリクトを何度も更新する
私はいまだに相手の反応が良かった言い方や、会話が弾んだら、都度その言い方に変えています。
トークスプリクトは1日何回も更新するときもあります。
アポが取れない時期は、よりいろんなトークを試して、トークスプリクトを何度も更新します。
最初新人の頃は、アポ獲得が上手な人の真似をするのが近道です。
時間でアプローチ先を分ける
1日8時間テレアポしなきゃいけない日があれば本当に地獄です・・。
3時間でもキツい日がありましたね。
そういう場合は、1時間はこのリストに荷電して、1時間はこの再コールリストをかけようというように、時間ごとに荷電先リストを変えて気分転換していました。
例えば飲食店に電話する場合は、「新規店舗」「東京の新橋エリア」「大阪の北新地エリア」「食べログ」「〇〇の飲食サイト」など時間ごとに荷電するテーマを変えていました。
疲れたら再コールリストに戻って、「〇〇さんいますか?」という確認を気楽に行なっていくなどして、ずっと力を入れて電話しないようにしていました。
誰宛にアポを取るのか考える
アポイントを取る相手は、社長なのか、決裁者なのか、担当アポなのか。
たとえば担当アポの場合は、稟議で上にあげる形が想定されます。
できるだけ決裁者にアポを取る、もしくは決裁者に近い方にアポイントを取るように意識していました。
最初はアポを取る感覚を覚えるために担当アポでも良いのですが、担当アポだと情報収集で終わることが多く、なかなか契約に結びつかないからです。
もちろん、大手企業など社長アポが難しい場合もあるので、その場合は割合を意識して獲得するようにしていました。
担当アポ3割、決裁者アポ7割を目標にするなどバランスを取ることも重要です。
問い合わせフォームからも連絡する
本社に電話すると、問い合わせフォームを案内されることもあると思います。
新人の頃、問い合わせフォームから連絡しても返事がないことが多かったので、問い合わせフォームを案内されると連絡しなくなりました。
しかし、他の同僚が「問い合わせフォームから連絡したら社長から返信が来た!」と言っていて、見事そのアポイントが契約に繋がったのです。
そこから私も問い合わせフォームを案内されたら必ず、問い合わせフォームから連絡して、どうやったら返信が来るか?ということを考えるようになりました。
どこにでも送れるような定型分ではなく、その会社に向けた内容で文章を考えます。
きちんと相手の会社のことを調べて「よく理解している」「きちんと自分たちの会社のことを考えてくれている」と感じていただけるような内容を必ず含め、オファーのような特別感を出して、問い合わせフォームから連絡するようになりました。
そうすることで、返信をもらえるようになり、契約に繋がるようになりました。
他人の再コール放置リストや追わないリストに荷電する
新規でリストを作成するのはとても時間がかかるので、新規リスト2時間、既存リスト2時間など、リストと時間で区切って電話していました。
自分の再コールリストがあと何件あるか常に確認し、保持するリスト件数を日々管理します。
会社によっていろんな決められたルールがあると思いますが、ルールに従いながら、他人の再コール放置リストや追わないリストに荷電していました。
新規で荷電するより、相手の情報(名前、前回のアプローチ結果)があるので、アプローチ方法を変えて電話します。
- 「電話しても意味ない」と思う方もいると思いますが、
営業はタイミングなので、当時は断っても違うタイミングで電話したらアポになったなんてことはザラにあります。
契約も同じで、タイミングが合わないと契約に至りません。
逆に、断られても違うタイミングで声をかけたら「ちょうど〇〇さんにこういう話を聞いてやってみようかなと思ってたんだよ」「社内の異動で上司が変わって」「今ちょうど予算を決める時期で」など、タイミングによって契約に結びつくことがよくあります。
その数パーセントの可能性を探すために電話するのです。
リストを育てるという考え方
電話がつらくなったときは、1回目の電話でアポを取ると考えず、リストを育てるために確認の電話をすると考えて電話をすると楽になりました。
テレアポは電話をして必要かどうか確認をしていく作業です。
そもそも、アポを取るためにはリストを育てていく必要があります。
そして、1回目の電話でアポイントを獲得する必要はありません。
下記は基本的なことですが、必ずメモ欄に残していました。
- 話した相手の名前
- 話した相手の役割・ポジション(契約するか決められる決裁権はあるのか)
- 話した結果(今の状況やニーズ、困っていること)
1回目の電話で全部情報が集まらなかったら、何回か電話して情報が集めます。
次回電話するときはメモ欄を見て、前回話したことを話題に出し、相手の本音を引き出せるようにしたり、関係構築に繋げます。
情報が集まったら、その相手にアポを取るべきか判断し、時間設定の話をします。
1回目は初めましてですが、2回目は初めましてではないので1回目よりは色々聞きやすいと思います。
自分からアポを断る
中には失礼な態度をする方や、全く興味を持ってくれない人もいます。
そんな人にアポを取る必要もないので、こっちから断ります。
もしタイミング的にも契約が難しそうであればアポにせず、3ヶ月後、6ヶ月後の再コールリストにして、時間をあけて連絡します。
テレアポが嫌にならないように工夫する
テレアポが嫌にならないように自分の再リストにネガティブなことは書かないようにしていました。
ネガティブなことを書いてしまうと、それを見てまた電話をするのはすごく嫌だからです。
将来の自分が電話しやすいようにメモ欄には「とても話しやすい方」など良いことをメモしていました。
自分を信じる
今結果が出ていなくても、自分を信じきることがテレアポでも営業でもどんな仕事でも大事だと思います。
自分を信じることできれば本当にいつかできるようになる日が来ます。
バンデューラ心理学の記事でも紹介したように、自分に自信がないと仕事の選択まで変わるくらい、「自分ができる」と信じられるかどうかはテレアポにおいても大事なことです。
「自分にはできない」「向いてない」と感じるときは誰にでもあります。
まさか「アポの天才」「アポの神様」と呼ばれる日が来るとは思っていませんでした。
「私はできる」と、自分を一度信じてみただけです。
周りが結果を出していても、時間はかかっても、焦らず自分を信じて創意工夫を続けることでいつか結果がついてきます。
以上が、私が思いつく限りでまとめたテレアポで工夫していたことです。
基本中の基本かもしれませんが、参考になれば嬉しいです。
ここまで読んでいただいてありがとうございました。


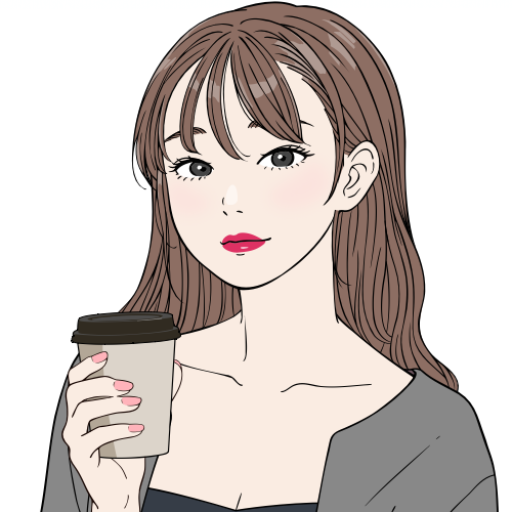



コメント