自己効力感とは、自分がある行動について「しっかりとやれる」という自信 (効力感)のことである。
自分の行動について『自分自身でコントロールできているという信念』、さらに自分が周囲からの期待や要請にきちんと対応できているという確信のことである。
何らかのキャリア選択をする際に、人は自己効力感が高い分野や職業を選択する傾向がある。つまり、自信がある職業を選択するのだ。
反対に、自己効力感が低い分野や職業は選択しない可能性が高い。つまり、自信がない職業は選択しないのだ。
たとえば、パイロットに憧れていて、その資質があったとしても、飛行技術の訓練をやり遂げる自信がなけ ればパイロットを諦めてしまうのだ。
自己効力感の低さによって、せっかくの選択肢を自ら手放すのである。
実は、人の自己効力感は、それほど実態を正確に反映しているわけではない。
これまでの失敗経験から、過剰に苦手意識や不安を身に着けてしまい、自ら実力を発揮する機会を失っている場合がある。 こうなると、ますます自己効力感を低下させる負のスパイラルに入ってしまうことになる。
一方、自己効力感が高い人は、小さなチャレンジを行い、小さな成功経験を積み重ねることによって自己効力感を高めていく。やがて遭遇する困難や逆境に対しても自ら乗りこえようと行動し、自己効力感の正のスパイラルが回り始めるのである。
実際に、就職活動を始める前にキャリア自己効力感が高かった学生の6割は早期に内定をもらい、一方、キ ャリア自己効力感が低い学生は同時点で3割程度にとどまっていた、という結果がある。
自己効力感の高い人
- 粘り強く努力して、多少の困難に直面した際にも耐えることができ、
- 自分の能力を上手く活用して、より一層の努力を重ねることができる。
キャリアを充実させるうえで、重要な特性であるといえる。
自己効力感を高めるための4つの情報源
①遂行行動の達成
自身の成功体験のことを指します。
例えば、学校を卒業した、英語の資格を取得した、トライアスロンを完走した等、そういう1つ1つの成功体験が自己効力感に繋がります。
大きなことではなく、IKEAの家具を一人で組み立てたとか、今日は自分の計画通りに物事を進められたんど、小さなことでもOKです。
「自分の力で成し遂げたこと」ならなんでもOKです。
②代理的経験
他者の体験を見たり聞いたり観察する経験(モデリング)のことで、友人の体験を聞いたり、大谷やイチローなどのインタビューを見ることも代理的経験になります。
たとえば、自分と同じように口下手の同級生が、社会人との挨拶や名刺交換をうまくやっているのを見て、 自分も同様にやれそうだと思うようになる。
また、失敗する姿を見たら、二の舞を演じないようにしようと学ぶこともあります。
③言語的説得
言語的説得とは、周囲の人からの励ましやサポートを受ける経験のことで、行動や技術などを繰り返し認められたり褒められたりすることを指します。
例えば、親や教師から「絵が上手だね」と言われ続けると、より絵をうまく描こうと努力して、結果的に描画が上達し、自己効力感が上がっていきます。
つまり、単に褒められ認められる経験だけでなく、そのことをきっかけに行動を起こして、遂行行動の達成が伴うことで自力感が向上するのである。

私の場合、小学生の頃塾の先生にお前の日記「面白い」と言われたことがきっかけで、文章力に自信を持って論文コンクールに出たり、海外へ一人旅した時にブログを始めて、友達に面白いと言われて、本気でブログを始め、自己効力感があがった経験があります。
また、仕事で励まし合う経験、自身の趣味を応援してもらう経験、英語などの勉強していることを褒められる経験などもあります。
④情動喚起
身体や精神的に起きた生理的感情的な変化の経験で、例えば人前での冷や汗や、高ぶりといった変化のことを指します。
例えばプレゼンテーションをするときに、手に汗を握り、緊張感が増す経験をすると、この経験により、プレゼンテ ーションに関しての自己効力感は低下します。
逆にリラックスできる状態に持っていけば、自己効力感は高まります。
生理的・感情的な過剰反応をしていると自己効力感が低下します。
もちろん、生理的・感情的変化や周囲の状況をどのように受け止めるかによっても自己効力感は異なってくる。
本人にとって喜ばしい状況における情動喚起は自己効力感を向上させる。
このバンデューラの理論から学ぶ自己効力感(自信)について知った時、自信によって日々の選択肢も変わり、キャリア選択にも影響していることを知り、ハッとしました。
小さな成功体験を積み重ねることを意識して生活していきたいと思います。


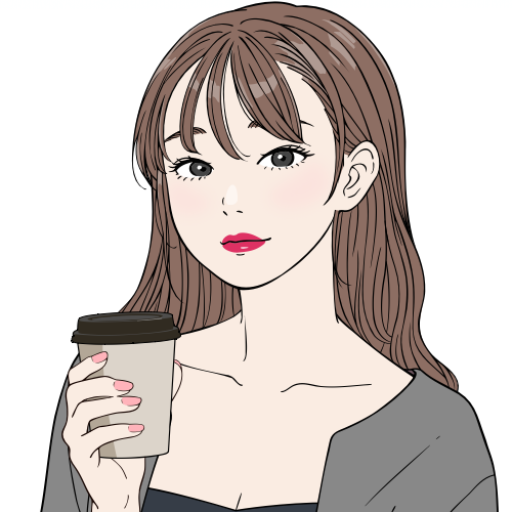

コメント